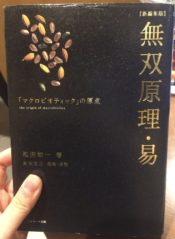ビタミンが体をつくる!?魚やキノコ類の積極摂取で体づくりをサポート

Contents
体づくりを助けるV.DとV.E
前回は、ビタミンA,Kと緑黄色野菜についてお話しました。今回は残りのビタミンD,Eについてです。これらはどのように体づくりを助け、何に多く含まれるのでしょうか。
今回も、ある食品類とビタミンをくっつけてお話していきます。では早速見ていきましょう!
こちらの記事は管理栄養士(国家資格)である広瀬陽香 (ひろせはるか)がかいています。大学で栄養学について学び、卒業後は女子アスリート寮で寮母として献立作成、食事提供、アスリートのメンタル面でのサポートをしていました。現在はアスリートが多数訪れる東大阪市のやまぐち整骨院にてアスリートと携わっております。
 管理栄養士 広瀬陽香
管理栄養士 広瀬陽香
魚類・キノコ類とビタミン
ビタミンDは数ある食品の中でも特にこの2つの食品に多く含まれています。
この2つの食品普段からどのくらい食べていますか?「嫌いで食べていない」などありませんか?食事を見させて頂くと抜けていたり忘れられやすい食品もあります。
骨・筋肉づくりのビタミンD
まずはビタミンDの体内での働きについてです。
生理作用
カルシウムと深い関係を持つビタミンです。ビタミンK同様に骨づくりを助けます。
ビタミンDは肝臓・腎臓を経て活性型ビタミンDに変換されることで体内でカルシウムの吸収を促します。血中のビタミンD濃度が高まっていくことで骨の形成が促進されます。
つまり、カルシウムと一緒に摂ると、カルシウムの吸収が促されます。
ビタミンDの2つの形
ビタミンDには2種類あります。
①ビタミンD2
②ビタミンD3
これらを食品別にすると

キノコ類(きくらげや干しシイタケを始めとしたキノコ全般)

紅サケ・塩サケ・カラフトマス・サンマ・イワシ・アジ
- 種類により吸収率は変わる
ビタミンDは2種類で吸収率に違いがあり、ビタミンD2(主にキノコ類)よりもビタミンD3(主に魚類)のほうが高くなります。
- 不足すると骨づくりに支障
骨軟化症・成長障害・くる病・X脚・O脚・骨粗鬆症
生理作用にカルシウムの調節をもつビタミンDが不足することで、本来腸管などから吸収されていたカルシウムが吸収されにくくなり、低カルシウム血症となります。
それにより、体は体内のカルシウム濃度を一定に保とうと骨からカルシウムを引き抜こうとします。そうして体内でのカルシウム利用が低下することで小児ではくる病・成人では骨軟化症が起こります。
- 過剰になると臓器に異常
高Ca血症・石灰化障害(心臓・肺にCaが沈着)・腎機能障害
ビタミンDの過剰により余分なカルシウムが様々な臓器に沈着していくことで石灰化障害などが起きます。主にサプリメントであり普通の食事ではほぼありません。
また、日光によるビタミンDの産生は調整されており、必要以上のビタミンDは産生されません。したがって日光によるビタミンDの過剰は起きません。
- アスリートは骨や筋肉のために最低限不足しないこと
ビタミンDは筋肉の強度や大きさ、機能にも関係することがわかっています。アスリートに対して付加量が示されているわけではありませんが、少なくとも一般的に不足の可能性が低いとされる量は確保しておきたいですね。
そのためにも上に挙げた食品を中心にバランスよく様々な食材を摂取しましょう。魚やキノコ類など1日のどこかに1回は摂取するように心がければ、大きく不足することはないでしょう。
また、ビタミンDは太陽の有無にも深く関係しています。
皮膚には前駆体といってビタミンDの前段階のものが存在します。日光を浴びることでこの前駆体がビタミンD3に変化させてくれます。
アスリートでは、
☑室内での練習や試合がメイン
☑早朝・夕方など太陽が出ていない時しか屋外練習はしない 等
太陽を浴びる機会が極端に少ない選手は注意が必要です。
もちろん紫外線は悪い影響もあるので、日焼け止めや対策というのも必要です。なので、ずっと無防備で出て下さいという訳ではありません。適度に太陽にあたることも大切ということです。
魚類・緑黄色野菜・種実類とビタミン
ビタミンEは数ある食品の中でも特にこの3つの食品に多く含まれています。
この3種類も少し意識していないと抜ける日も多くあります。外食や中食でも自ら進んで選ぶということはあまりなさそうな食品ですね。
抗酸化のビタミンE
生理作用
体の酸化(サビ)に抗うビタミンです。ビタミンAにも抗酸化力という言葉があったと思いますが、ビタミンEも同じように働きます。
そして、もう1つビタミンの中で抗酸化作用を持つビタミンCに関しては、それ自体もその作用をもちながら、抗酸化の力を使った後のビタミンEを再生させる力ももっています。一緒に摂ると良いですね😊
ビタミンEを多く含む食品
キングサーモン・ウナギ・マグロ缶詰
ヒマワリ油・サフラワー油
かぼちゃ・ほうれん草・枝豆・アーモンドなどの種実類全般・アボカド・梅・プルーン・キウイ
*ビタミンEには植物油にも多く含みますが、酸化がはやいのでできるだけ早めに使い切るほうが良いでしょう。
アーモンドをおやつ代わりに食べると、手軽なビタミンE 補給になります😊(ナッツ類は脂質も割と含むので10粒くらいで良いかと思います。)
- 不足すると貧血の可能性
溶血性貧血
血中のビタミンE濃度が低下することによって細胞膜の脂質が酸化します。それにより赤血球膜の抵抗性が弱まることで起きます。
しかし、通常の食品摂取において欠乏症は発症しません。
- 過剰になると出血傾向
過剰摂取により、出血傾向が上昇します。ただし、通常の食品からの摂取においてビタミンE過剰症は発症しないとされています。
- アスリートは最低限不足しないこと
生理作用でもお話したようにビタミンEは抗酸化作用を持ちます。日光によく当たり、エネルギー消費が一般人よりはるかに多く、激しい運動を行うアスリートは、より体がサビやすい(酸化しやすい)と考えます。
ですが現状では、アスリートに対してビタミンEが十分な抗酸化作用を示す量というのは断言できません。
そのため、少なくとも一般的に不足の可能性が低いとされる量は確保しておきたいですね。そのためにも上に挙げた食品を中心にバランスよく様々な食材を摂取しましょう。それができれば大きく不足するようなことはないでしょう。
「炒める」「揚げる」で脂溶性ビタミンの吸収率をUP
水溶性ビタミンにはない脂溶性ビタミンの大きな特徴は油と一緒に吸収されることです。そのため、 油と一緒に調理することで吸収率がぐっと上がります。
前回と今回紹介した脂溶性ビタミンのビタミンD、A、K、Eはどれもこの方法で吸収率があがります。
またビタミンDのように、同じビタミンでもその種類により一方が吸収率が劣るもの(ビタミンD3のほうがビタミンD2よりも吸収率が高い)も、この調理方法により吸収率を上げることが可能です。
油の料理をもう1品増やすことではない
注意すべきことは、吸収率を上げるために油物をもう1品増やしてしまうことです。
そうではなく、油を使う料理があるならそこへ緑黄色野菜やキノコをいれてしまうなど、「どうせ油を使うなら効率よく使おう」 ということです!
前の食事で油を多くとるような外食や揚げ物等食べていればまた別ですが、基本的には油を使った調理法は1食につき1品で十分です。
ビタミンを不足させないためには多くの食材を食べる
前回と今回の話を合わせて、自分の嫌いな食べ物や特に必要と感じていなかった食材はありましたか?
そのまま食べないでいることが勿体ないということを感じて頂けましたか?
アスリートは一般人よりもはるかに沢山の栄養素を必要とすると考えられます。自分で自分の摂れる栄養素の幅を狭めていてはいけません。積極的に摂っていきましょう!
今回お話した脂溶性ビタミンを始めとしてビタミンの不足の可能性をできるだけ遠ざけるには、より多くの食品を食べることです。
手作りが難しいのであれば、足りないものをスーパーやコンビニで買いそろえても良いでしょう。
何か1つの食品だけの摂取では必要な栄養素は揃いにくいですし、良い効果があるからと食べ続ければ、それは悪影響に変わっていくかもしれません。
それを常に頭に置き、様々な食品を食べていきましょう!食事はバランスが最も必要なことです。
まとめ
- 骨や筋肉のためにビタミンDは最低限不足しないように摂取する
➡ビタミンDは筋肉の強度や大きさに関与する。魚やキノコ類など1日のどこかに1回は摂取することや、卵や乳製品をはじめとした様々な食品をバランスよく摂取するように心がければ、大きく不足することはない。
- 室内での活動が多い・太陽が沈んでいる時がメインのアスリートはビタミンD不足に注意
➡太陽を浴びる機会が少ないため、ビタミンDの体内での合成量が大幅に減少する。しっかり食事からとることを意識する。
- ビタミンEは抗酸化に関与するため最低限不足しないように摂取する
➡魚類・緑黄色野菜・種実類など上に挙げた食品を中心にバランスよく様々な食材を摂取するように心がければ、大きく不足するようなことはない。
- 「炒める」「揚げる」で脂溶性ビタミンの吸収率をUP
➡脂溶性ビタミンは油と一緒に吸収される。1日1食油を使う料理があるのならそこに多くの食材を入れる。
- 様々な食品を摂取することで不足を避ける
➡食品はサプリメントではないため1つの食品に様々な栄養素を含みます。できるだけ多種多様な食材を摂取することで不足の可能性を遠ざけられる。
最後まで読んでいただきありがとうございました😊