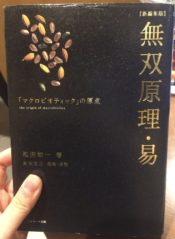ビタミンは十分?まずは自分の食事と比べてみよう!

ビタミンを知って適切に利用する
前回に引き続きビタミンについてお話していきます。
「ビタミン」という言葉は非常に身近な言葉ですよね。
スーパーやコンビニにもビタミンが含まれた飲み物など多く販売されています。
サプリメントもビタミン類は多く出ています。また成分表示をみると栄養強化でビタミンが添加されているものもあります。
ビタミンは健康に必要というイメージで”とりあえず”これらの商品などを摂っている方も多いかもしれません。
脂溶性ビタミンについての記事を見て頂くとわかるように、一口にビタミンと言ってもその種類は様々で現在の自分の食事で摂れているビタミンもあれば、そうでないビタミンもあります。またビタミンによっては、摂りすぎは過剰症に繋がることが分かってもらえると思います。
ビタミンを売りにした商品を”とりあえず”健康に良いからなんでもかんでも飲む、食べるのではなく、ビタミンそれぞれを知ったうえで摂取することが適切な利用に繋がります。
今回は、ビタミンの中でも特にサプリメントなどにも多い水溶性ビタミンの体の中での働きと、どのような食品に多く含まれるのかなどについてお話していきます。
自分の今の食事で何が足りていていなく、どんなものを食べれば良いのかということを考えながら見てもらえたらと思います。
こちらの記事は管理栄養士(国家資格)である広瀬陽香 (ひろせはるか)がかいています。大学で栄養学について学び、卒業後は女子アスリート寮で寮母として献立作成、食事提供、アスリートのメンタル面でのサポートをしていました。現在はアスリートが多数訪れる東大阪市のやまぐち整骨院にてアスリートと携わっております。ビタミンについてどのくらい知っていますか?理解をして適切な摂取をしましょう!
 管理栄養士 広瀬陽香
管理栄養士 広瀬陽香
ビタミンB群の働きは多様
ビタミンB群という言葉耳にしたことがあるのではないでしょうか?これらはこれからお話していくビタミンの総称となっています。
では早速、ビタミンB群の1つ1つの生理作用と含まれる食品について細かく見ていきましょう。
ここでは以前ご紹介した水溶性ビタミンを抜いた他の水溶性ビタミンについてお話していきます。
ビタミンB2
生理作用
B1と同様に三大栄養素をエネルギーに変える反応の補酵素になるためエネルギー消費量が多い(運動量が多い)ほどB2必要量が増えます。
不足時に起きること
成長抑制・舌炎・口内炎・口角炎・皮膚炎・皮膚の乾燥・髪のトラブル
過剰摂取時に起きること
レバー(種類にもよりますが、50gで約1.5㎎のB2摂取になります。一般人だとこれだけで必要な量(ここでの必要な量とは食事摂取基準の成人のRDAをもとにしています。)を摂れてしまい、エネルギー消費の多いアスリートでも必要な量の半分以上は摂れる。)を除き、100g当たり1㎎を超える食品はありません。
なので、通常の食事で過剰による健康障害が発現した報告が現在はありません。
摂取量が増加するとともに吸収率は低下していく特徴をもちます。余剰分は尿に排出されるという点からも、過剰の影響は受けにくいと考えられます。
1回の吸収量も決まっており、大量摂取によるパフォーマンス向上の可能性も明確ではないとなっています。なので、現時点ではアスリートのパフォーマンス向上のための必要以上の摂取の意義は小さいと思います。
多く含まれる食品
レバー・ウナギ・カレイ・サバ・サンマ・牛乳・乳製品・卵など動物性食品
特に動物性食品に多く含みます。魚などもしっかり摂りましょう!! 緑黄色野菜やキノコ類、納豆など植物性食品にも比較的多く含まれます。一般の方であれば、牛乳1杯でビタミンB2の必要な量の1/4量は摂れます。
ここに挙げられた食品を普段から口にしており、基本的にバランスの良い食事をしている分には不足の可能性は高くないでしょう。
調理時に注意すべきこと
- 調理損失は比較的少ない
- 水溶性ビタミンなのでゆで汁などに溶出
- 光に弱い
*光が良く当たるところでの放置は気を付けたいところです。
アスリート
アスリートは、一般人よりも運動量は多いため明らかにエネルギー消費量が多くなります。その分エネルギー産生に関わるビタミンB2の必要量は上がってきます。持久性能力に重要です。
また、このビタミンは脂質代謝に関与するため、脂質摂取が多い選手や長距離など持久系の競技により脂質によるエネルギー産生が多い選手には不足の可能性も考えられます。
ナイアシン
生理作用
- エネルギー産生の補酵素
- 生体内の酸化還元反応に関与
- 脂質・タンパク質の合成に関与
- アセトアルデヒド分解の補酵素
B1・B2と同様に三大栄養素をエネルギーに変える反応の補酵素になるため、エネルギー消費量が多い(運動量が多い)ほどナイアシンの必要量が増えます。
アセトアルデヒドというのはアルコールが分解されると出てくるもので二日酔いのもとであり、このアセトアルデヒドを分解する反応の補酵素がナイアシンです。
お酒を飲む人ほど消費量は多くなります。
不足時に起きること
ペラグラ(皮膚炎・下痢・精神神経症状)や皮膚炎
基本的には起きませんが、アルコールの多飲や偏食が原因で起きることがあります。
過剰摂取時に起きること
通常の食事では起こりにくいと考えます。
ただし、サプリメントなどによる大量摂取においては様々な報告があります。まずは、自分の食事で本当にそのビタミンが不足しているのか(通常の食事では起こりにくいので)考えてからの摂取が良いでしょう。
また必要以上の摂取による脂肪の分解が妨げられてしまうこともあります。過剰分は尿に排出されていく水溶性ビタミンの中でも、ナイアシンは過剰に注意が必要です。安易にサプリやビタミンを売りにする商品に頼ることはやめたほうが良さそうです。
多く含まれる食品
レバー・豚ロース肉・カツオ・アジ・マグロ・サバなど動物性食品
落花生など植物性食品
ナイアシンに関しては、魚を始めとしたタンパク質食品を十分に摂取し、偏りのない食事をしていれば不足することはまずないと考えます。
特に魚に関しては、消費エネルギーに合った摂取量にしていれば、1食分で必要なナイアシン量の多くを摂れます。
ビタミンと聞くと野菜のイメージが強いですが、ビタミンの中には魚が野菜を上回るようなものもあります。好き嫌いせず、しっかり食べましょう。
アスリート
ビタミンB2同様、一般人よりも明らかにエネルギー消費量が多くなるアスリートは、エネルギー代謝に関わるナイアシンの必要量が上がってきます。
エネルギー産生に関わるためしっかり摂取することが持久性能力に重要です。
魚を積極的に1日1食はいれることをおススメします。
調理時に注意すべきこと
- 熱や光など強く分解されにくい
- 調理による影響は受けにくい
- 水溶性ビタミンなのでゆで汁などに溶出
他のビタミンに比べ、熱や光に強いことなど、安定性が高いと言えます。ただし、水溶性ビタミンに変わりないので水には溶けだしやすくなっています。
ビタミンB6
生理作用
- タンパク質の再合成に関与
- 脂質の代謝に関与
- 神経伝達物質の合成に必要
タンパク質の合成に関係することから、タンパク質摂取量が多いとビタミンB6の必要量は多くなります。また、減量中による食事制限で、エネルギー摂取不足が起こり、他のものからエネルギーを作ろうとタンパク質やアミノ酸の分解が進んでいる時はB6の必要量も増加します。
欠乏時におきること
ペラグラ様皮膚炎・貧血・神経系の異常
過剰摂取時に起きること
光過敏症・感覚性ニューロパチー・シュウ酸腎臓結石
通常の食事をしているものの中で過剰摂取による健康障害が発現した報告はないとされています。しかし、サプリメントなどによる大量摂取では過剰症が認められています。
調理に注意すべきこと
- 光(特に紫外線)に不安定:日がよく当たるところでの食品の放置は注意が必要です。
冷凍食品や加工食品ではビタミンB6は目減りしてしまいます。できるだけ鮮度の良い魚・肉で摂取をしましょう。
多く含まれる食品
レバー・とりのささみ
カツオ・マグロ・サケ・サンマ・サバ 等の動物性食品
バナナ・サツマイモ 等の植物性食品
ビタミンB6は動物性に特に多く含まれます。ナイアシン同様です!
たんぱく質量をそれぞれに合った量を摂取していれば不足する可能性は低いと考えます。特に魚に関しては、消費エネルギーに合った摂取量にしていれば、1食分で必要なビタミンB6量の半分を摂れます。吸収に関しても、動物性のほうが良いです。やはり魚は1日1食は取り入れたいですね。
残りは、バランスよく肉や野菜・大豆・卵・牛乳など摂取していればとれていると考えます。
アスリート
ハイパワー系の競技(ウエイトリフティング・100m走など)でたんぱく質量が多い選手や運動を始めたばかりの選手では体内で筋合成が活発になっているのでB6の必要量は上がっていると考えます。
魚介類を中心としたタンパク質を個々の必要量に合わせて摂取できていればおそらく不足の可能性は低いと思います。
アスリートの注意点ですが、肉ばかりを摂取しているアスリートやプロテインやアミノ酸を多用しておりそこに十分なビタミンB6がなければ欠乏が考えられます。
また、B6は不足を改善することエネルギーが上手く作れるようになるのでパフォーマンスに良い影響を及ぼす可能性もあります。
今一度自分の食事を見直してみましょう。
ビタミンB12
生理作用
水溶性ビタミンの葉酸と協力して赤血球を作ります。貧血に関係のあるビタミンです。
欠乏時に起きること
巨赤芽球性貧血・手足のしびれ・ハンター舌炎・好中球の減少などです。
不足により造血作用が上手く行われず悪性貧血になります。
ビタミンB12は他のビタミンに比べて、必要量はごくわずかで体内貯留量も他の水溶性ビタミンと比較すると多いです。なので、極端な偏食をしない限りは不足することはまずないと考えます。
ですが、一般的には植物性食品には含まれなく、厳密な菜食主義者では欠乏することがあります。
また、ビタミンB12の吸収には、胃から分泌される内因子が必要です。
なので(少し専門的なお話ですが・・・)胃切除者・慢性萎縮性胃炎患者のように胃に問題がある人は、この吸収に必要な内因子が不足し吸収が十分にできず欠乏症が起きます。
過剰時に起きること
胃の内因子により吸収量が調節されているので、通常の食事をしていれば過剰摂取による健康障害発現の報告はないとされています。また、サプリメント等による摂取においても、体内への吸収量が厳密に調整されているため健康障害の報告はないとされています。
調理時に注意すべきこと
- 水に溶けだしやすく、光によって分解されます。
汁ごと頂ける料理が良いですね。光や空気に弱いので、肉や魚を冷凍保存する場合にはきちんと密封することが大切です。光に当たるところでの放置にはお気をつけください😊
- 比較的に熱には安定なビタミン
調理時の熱で分解されることはあまりないと考えられます。
多く含まれる食品
レバー・カキ・アサリ・サンマ・シジミ・イワシ・サバ・ホタテ 等
魚介類、チーズ、肉類、卵など多く含みます。
動物性食品をきちんと摂っていれば不足することはまずありません。
量的にも、これら挙げた食材では普通に1人前(卵やチーズは除く)食べていればそれで充分摂取できています。
(*今後必要な量は、変わる可能性があります)
ただ、1回の当たりの吸収量には限りがあるのでサプリなどでも一度に大量摂取ではなく食事ごとに一定のビタミンB12(2.0μg程度)の摂取が望ましいとされています。
アスリート
審美系のアスリートや女子アスリートは、体重を増やさないことを考えエネルギーの少ない野菜中心に食べている選手もおり、肉・魚などの動物性食品を極端に嫌って食べないとなると不足が心配されます。
貧血の可能性が上がってくるため、適切な摂取量を知ってもらうと共にどうしても難しい場合はサプリメントの活用も頭に入れておく必要があると考えます。
多く摂取することによるパフォーマンスへの好影響の報告は特にありません。
ご自身の今の食事で、これらのビタミンは足りていましたか?
「あまりとれていなかった」というような食品があれば、ぜひ、今日から取り入れてビタミン不足の可能性を遠ざけていきましょう!!
サプリメントなどもありますが、食事で賄える部分は食事で賄っていきましょう。それが一番体にとって自然な食事の風景だと思います。
とても長くなりましたが読んでいただきありがとうございました!水溶性ビタミンについて説明させていただきましたがいかがでしょうか?「そうなんや!」と何か新しい気づきや、食行動を見直すきっかけになればと思います。
残りの水溶性ビタミンの葉酸・ビオチン・パントテン酸についてまたまとめようと思います!