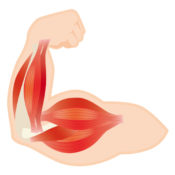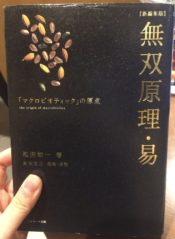疲労しにくい体と持久力が欲しい!ミトコンドリア知って効果的な食事を

Contents
ミトコンドリアを知って疲労しにくい体と持久力を手に入れよう
ミトコンドリアという言葉は授業などで聞いたことがありますか?知らない言葉ではないものの、名前だけという方も多いのではないでしょうか。そして、ミトコンドリアと疲労や持久力に何の関係があるのかと題名を見て疑問を抱かれた方もいると思います。
疲労がとれないで困っている。疲れない体や持久力が欲しい!そんな方に今回はミトコンドリアに焦点を当ててお伝えしていきたいと思います。
こちらの記事は管理栄養士(国家資格)である広瀬陽香 (ひろせはるか)がかいています。大学で栄養学について学び、卒業後は女子アスリート寮で寮母として献立作成、食事提供、アスリートのメンタル面でのサポートをしていました。現在はアスリートが多数訪れる東大阪市のやまぐち整骨院にてアスリートと携わっております。
 管理栄養士 広瀬陽香
管理栄養士 広瀬陽香
この記事で何がわかる?
- ミトコンドリアとはどのようなものなのか
- 持久力や疲労とミトコンドリアの関係
- ミトコンドリアが十分に働く食事について
ミトコンドリアとはどのようなものなのか?
まずは、ミトコンドリアについて見ていきましょう。


私たちの体は約60兆個の細胞でできており、その細胞の中ほぼ全てにミトコンドリアが存在しています。その総量は体重の1割を占めると言われています。例えば、体重60kgの人であれば6kgものミトコンドリアを持っています。
ここで、ミトコンドリアの働きの起源を知ってもらうためにミトコンドリアの歴史についても少しお話しておきます。ミトコンドリアは昔別の生物であったと考えられています。太古の昔、酸素と糖を使ってエネルギーをつくり細菌(以下細菌A)がいました。ある時この細菌Aを別の細菌Bが飲み込んでしまい、細菌Aは細菌Bにエネルギーを与える代わりに糖と安全な場所を提供することで生き延びました。この細菌Aこそが後のミトコンドリアなのです。
ミトコンドリアの働き
- エネルギー産生
ミトコンドリアの大きな働きの1つとして挙げられるのが、エネルギー産生です。このエネルギーというのは、動いていなくても生きている限り使われます。その生きていく為に必要不可欠なエネルギーをつくっているのが、このミトコンドリアだということです。
もうこの時点でかなりミトコンドリアが重要な存在であることがわかりますね😊
ミトコンドリアと持久力・疲労の関係
ミトコンドリアがエネルギー産生することがわかりました。では、それと持久力や体力、疲労となんの関係があるのでしょうか?
持久力・体力との関係
ミトコンドリアは食事を摂ることで増加させることは難しいのですか運動によって、増加させることができます。体積を増やすには適度な有酸素運動が良いとされています。(但し、運動を定期的に行わなければ1か月ほどで元の体積に戻ってしまいます。)そうして筋肉細胞の中のミトコンドリアが増えればミトコンドリア内でより多くのエネルギーを作ることができ、そのエネルギーを使って動く筋細胞は長時間疲れずに動き続けることができます。
つまりミトコンドリアの増加により持久力は上がるということなります。
疲労との関係
疲労の原因として挙げられるのが、エネルギー不足です。
ミトコンドリアが十分に働いているということは、エネルギーを十分生産することで疲労しにくい体ができるという仕組みです。逆にミトコンドリアが十分に働かないということはエネルギーが不足し疲労しやすい体になります。
ミトコンドリアが十分に働く食事について
ミトコンドリアが十分に働くということは、エネルギーが十分に産生されるということです。では、どのようにしてそのエネルギーは作り出されているのでしょうか。
- ミトコンドリアの中で回路が回りエネルギーが作り出される
- その回路を回すにはビタミン、アミノ酸が必須
食べたものが、エネルギーになるまで
糖質、脂質、タンパク質(三大栄養素)は全てミトコンドリアでエネルギーに変わります。この三大栄養素は、どれもほぼ同じ回路でエネルギーに変わるのですが、それには他の栄養素を必要とします。
エネルギーになる三大栄養素を摂ったとしてそれが他の栄養素の力を借りることなく、それ単体で消化(分解)されてエネルギーになるのではないということです。
(例:白飯だけを食べたからといってそれがそのままストンとエネルギーにはなりません。)
多くの化学反応が次々に起こる過程でエネルギーが産生されます。
そして、その回転の中では主に、ビタミンB群やアミノ酸が働いています。
ビタミンB1、B2、B6、ナイアシン、ビオチン、パントテン酸です。(ビタミンに関する記事は後々1つ1つ詳しく挙げていきます。)アミノ酸に関しては、非常に多くの種類が働いています。
アスリートでは、エネルギーがより多く消費されるため、必要量は自然とあがってきます。
どうすればエネルギーが十分に産生されるか
- ビタミンB1:玄米、そば、大豆、豆腐、豚肉、ボンレスハム等
豚肉が疲労回復と言われるゆえんはこれです。ビタミンB1は、ほぼすべての食品に少しずつ含まれています。このビタミンは特に不足に気を付けなければいけないビタミンとなっています。
- 主食であれば白米に玄米を混ぜてみたり、胚芽米にしてみる
- 豚肉を適宜料理に取り入れる
- 汁ごと食べられる汁物を有効活用する(水分に溶けだしやすいので)
- 漬物はぬか漬けを選んでみる
- ビタミンB2:レバー、ウナギ、カレイ、サバ、カニ、サンマ、牛乳、納豆、緑黄色野菜等
特に脂質をエネルギーに変換するときに使われています。脂質摂取の多いアスリートや低糖質で高脂質食をしているアスリートでは不足しやすくなっています。
緑黄色野菜、キノコ類、乳製品、魚、大豆製品をしっかり取り入れていきましょう。
- ナイアシン:レバー、豚肉、カツオ、アジ、マグロ、サバ、カジキ、落花生
魚や肉に多く含まれていることからこれらのタンパク質食品を十分に摂取していれば不足の可能性は低いです。(1食分の食材に十分量含まれています。)サプリなどでのナイアシンの摂取はたんぱく質量を十分にとっている選手には過剰かもしれません。
- ビオチン:レバー、納豆、鶏卵、落花生
このビタミンも普通の食事をしていれば、不足する可能性は低いと考えられます。腸内細菌により作られているビタミンでもあるので、抗生物質など服用している際には食べ物から十分量補う必要性があります。
- パントテン酸:レバー、ささみ、マス、ウナギ、納豆、アボカド
パントテンとは至る所にという意味です。幅広く多くの食材に含まれているため普通の食事で不足することはほぼありません。パントテン酸はエネルギー代謝の中心物質の構成成分にもなっています。
アミノ酸というのはタンパク質が分解されたもので、20種類のアミノ酸がくっついてタンパク質となります。含有されるアミノ酸の種類や量は食品によって異なり、簡単に言えば、何か一定の食材を摂るのではなく様々な種類の食品を摂ることです。
植物性のタンパク質(豆腐、厚揚げ、納豆、米など)も、動物性のタンパク質(肉:牛・鶏・豚、魚:青魚・白身魚・赤身魚、卵、乳製品、貝類など)もどちらも重要です。アミノ酸に関しては栄養学記事として書いていこうと思います!
ここで注意しておいて欲しいことは、エネルギーを作るのはこれらの栄養素が働きますが
そのエネルギーの材料は、糖質・脂質・タンパク質の三大栄養素です。エネルギー源もしっかり摂ってそれをエネルギーにするのを助けてくれるビタミンもしっかり摂りましょう。
ということは、結論バランスの良い食事です。
結局、いきつく先はここです。何かを効果的に働かせるベースはこれだということです!!
更に効果的に疲労回復や持久力アップのために
- 食事を摂ることによるミトコンドリアの増加は難しい(食事で働きをよくすることはできるが)
- 摂った栄養素をより効率よくエネルギーにし、疲労回復や疲れない体を作ったり持久力を上げたい!
ということから、1つご紹介しておきます。私の勤めるやまぐち整骨院や、やまぐちスポーツ整骨院にハイチャージという機器があります。この機器に関する記事はこちらになります。是非、覗いてみて下さい!
ハイチャージの簡単な特徴
- これまでの電気治療の弱点を克服
- 体中の全てのミトコンドリアに働きかけることで身体の不調を改善
- 効率よく振動させることにより代謝を正常化
ぜひ当院にてご体感ください。